毎年世界中が注目するノーベル賞。その権威と、受賞者に贈られる多額の賞金の原資がどこから来ているかご存知でしょうか?
実は、ノーベル賞は単なる寄付や国費に頼っているわけではありません。その永続的な運営を可能にしているのは、創設者アルフレッド・ノーベルの遺産を賢く管理・運用している専門の団体、ノーベル財団(The Nobel Foundation)による、先駆的で堅実な資産運用戦略です。
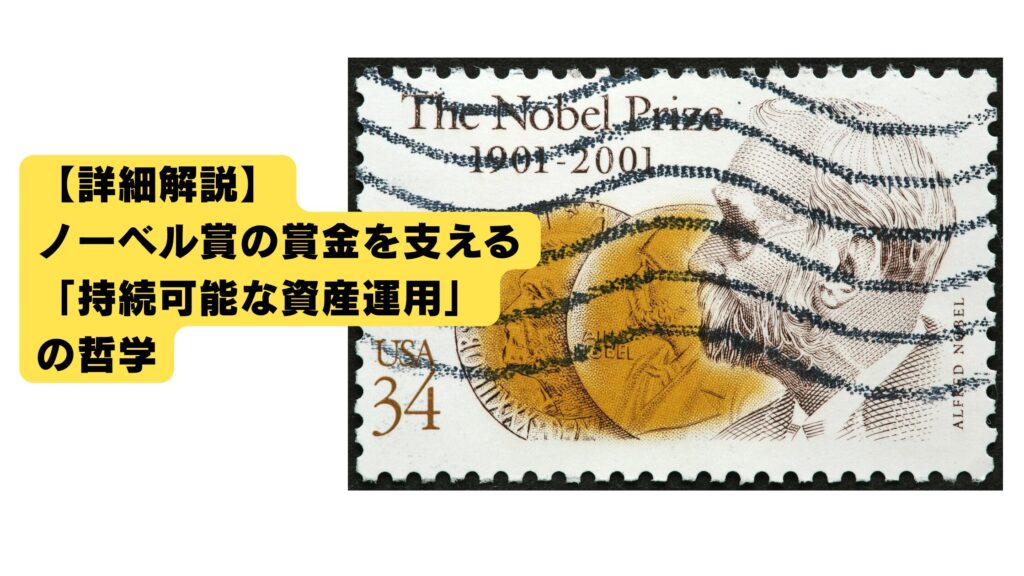
1. ノーベル財団の設立と賞金の原資
ノーベル賞は、スウェーデンの発明家アルフレッド・ノーベルの遺言に基づき創設されました。彼は、自身の遺産の大部分を基金として設立し、「人類に最も貢献した人々」に賞と賞金を贈ることを望みました。
特筆すべきは、彼の遺言が「元本(遺産)は使わず、安全な証券に投資し、その収益で賞金を支払う」という、現代の持続可能な資産運用の基本原則を100年以上も前に示していたことです。この遺産を管理し、賞の運営全体を担っているのがノーベル財団です。
2. 永続性を担保する「長期的な目標」
ノーベル財団の財政管理の核心は、この賞を未来永劫にわたり授与し続けるという「永続性」にあります。
財団は、この使命を達成するために、「インフレ調整後で少なくとも年率3%のリターンを目指す」という明確な運用目標を掲げています。このリターンレベルを達成することで、毎年の賞金支払い、選考委員会や事務局の運営費といった「事業費」(総資産の年率3%前後)を賄い、さらに元本の価値を長期的に守ることを可能にしています。
3. 堅実かつ先進的な「分散投資」戦略
ノーベル財団の運用戦略は、ノーベルの遺言に忠実でありながら、時代の変化に合わせて進化し続けています。
彼らは、リスクを抑えながら安定した収益を確保するため、伝統的な資産である株式や債券だけでなく、オルタナティブ投資(代替投資)も積極的に取り入れた「分散投資」を行っています。
- 基本ポートフォリオの構成(例)
- 株式:約55%
- 債券:約10%
- 不動産・インフラ:約10%
- オルタナティブ(ヘッジファンド等):約25%
特に注目されるのは、低金利環境下で収益が期待しにくい債券の代替として、ヘッジファンドに高い比率(約25%)を割り当てている点です。これは、様々な市場環境で安定したリターンを目指し、ポートフォリオ全体のバランスを取るための工夫です。
4. ノーベル賞の理念に沿う「責任投資」
ノーベル財団の運用哲学のもう一つの柱は、**責任投資(Responsible Investment: RI)**です。人類への貢献を称える賞を支える資金として、単なる経済的利益だけでなく、倫理的な側面も重視しています。
財団は、投資判断を行う際に、国連グローバル・コンパクトに定められた「環境」「人権」「労働」「腐敗防止」といった要素を厳格に考慮しています。例えば、核兵器に関連する企業への株式・債券投資を排除するなど、社会的責任を果たす企業に投資を限定しています。
5. 資産管理における危機と「真の意図」
実は、ノーベル財団は、創設者アルフレッド・ノーベルの遺言に基づき1900年に設立されましたが、その資産運用は初期に大きな危機を迎えました。ノーベルの遺言には「遺産は安全な証券に投資すべし」とあり、当初の財団はこの指示を忠実に守り、国債や銀行預金といった極めて保守的な資産運用に終始していました。
しかし、この戦略が裏目に出ます。20世紀前半に世界を襲った高インフレ(物価上昇)は、固定利回りの低リスク資産である国債の実質価値を激しく蝕みました。結果として、財団の資産は設立当初の実質価値から3分の1以下にまで激減し、「このままでは賞金が支払えなくなる」という深刻な枯渇の危機に直面しました。
この危機的状況を打開するため、財団は運命的な決断を下します。それは、遺言の文面ではなく、「賞を永続させ、人類に貢献した人を称える」というノーベルの真の意図を最優先することでした。
1950年代以降、財団はスウェーデン政府に対し、株式や不動産といったリスクを取りつつ高いリターンが期待できる資産への投資を許可し、かつ非課税とするよう繰り返し働きかけました。この粘り強い交渉が実を結び、財団は伝統的な資産運用から脱却し、「攻めの分散投資」へと舵を切りました。
この歴史的な方針転換が成功の鍵となり、財団の資産は回復・成長を遂げ、賞金も増額されました。ノーベル財団は、時代の変化に応じて戦略を柔軟に変えることの重要性を、私たちに教えてくれています。

