「遺言書」と聞くと、なんだか難しそう、自分には関係ない、と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、遺言書はあなたの想いを大切な人に確実に伝えるための、とても大切なツールです。
「自筆の遺言書でも大丈夫?」というご質問をよくいただきますが、答えは「はい、大丈夫です!」ただし、法的に有効な遺言書にするためには、いくつかのルールを守る必要があります。今回は、自筆の遺言書(自筆証書遺言)の書き方と、FPが遺言書作成においてどのようなお手伝いができるのかについてお話ししたいと思います。
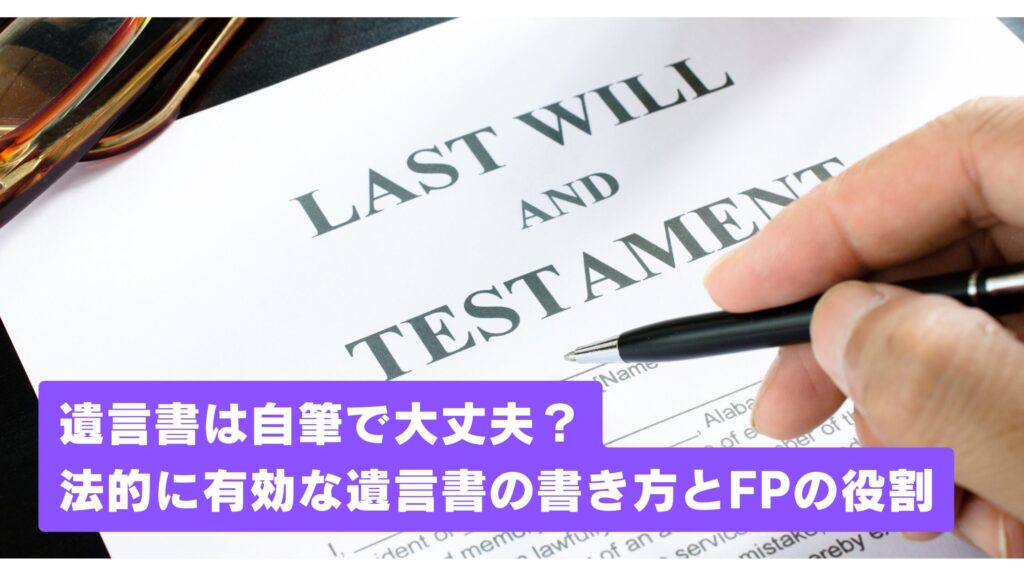
1. 自筆証書遺言は「自筆」がポイント!
自筆証書遺言とは、その名の通り、遺言者が全文、日付、氏名をすべて自分で書く遺言書です。2020年の民法改正により、財産目録については自筆でなくてもよくなりましたが、それ以外の部分は手書きでなければなりません。
【自筆証書遺言のルール】
- 全文自筆: パソコンや代筆は無効です。一字一句、ご自身の手で書きましょう。
ただし、財産目録などはパソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能です。 - 日付の記載: 「令和〇年〇月〇日」と、特定できる日付を必ず入れましょう。「〇月吉日」は無効となるので注意が必要です。
- 氏名の記載: 氏名を自筆で書きます。認印でも構いませんが、実印のほうがより確実です。
- 押印: 氏名の横に押印します。認印でも構いませんが、実印のほうが望ましいです。
これらのルールが一つでも欠けると、遺言書は法的に無効になってしまいます。
2. 法的に有効な遺言書の書き方テンプレート
それでは、具体的にどのような内容を書けば良いのでしょうか。一般的な遺言書の構成をご紹介します。
【遺言書の構成例】
- 遺言書の表題: 冒頭に「遺言書」と書きます。
- 本文: 誰に何を相続させるのかを具体的に書きます。
- 財産の特定: 「〇〇銀行〇〇支店の普通預金」「〇〇市〇〇町〇丁目の土地」など、誰が見てもわかるように具体的に特定します。
- 相続させる人物の特定: 「長男〇〇に相続させる」「妻〇〇に遺贈する」など、氏名と続柄を明確に書きます。
- 遺言執行者の指定: 遺言の内容を実現してくれる「遺言執行者」を指定します。親族でも、弁護士や司法書士などの専門家でも構いません。
- 付言事項(ふげんじこう): 法的な効力はありませんが、遺言者が家族への感謝の気持ちや、遺言の内容にした理由などを自由に記載できる部分です。ここに想いを込めることで、遺された家族が納得しやすくなります。
- 日付: 作成した日を正確に記載します。
- 署名・押印: 氏名を自筆で署名し、押印します。
【注意点】
- 曖昧な表現は避ける: 「財産の半分を長男に」といった曖昧な表現は、後でトラブルの原因になります。具体的な金額や割合、物件などを明記しましょう。
- 相続人以外への遺贈: 相続人以外の人(例えば、お世話になった友人など)に財産を渡したい場合は、「相続させる」ではなく「遺贈する」という言葉を使います。
3. 遺言書作成におけるファイナンシャルプランナー(FP)の役割
「自分で書くのは難しそう…」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。そんな時こそ、私たちファイナンシャルプランナー(FP)にお声がけください。FPは、遺言書の作成そのものを代行することはできませんが、以下のような役割を担うことができます。
- 現状の財産整理のお手伝い: 「自分にどんな財産があるのかわからない」という方も少なくありません。まずは、預貯金、不動産、有価証券、生命保険などをリストアップし、財産の全体像を把握するお手伝いをします。
- 相続税のシミュレーション: 遺言の内容によっては、相続税が発生する可能性があります。FPは、相続税の一般知識や事例の情報を提供します。必要に応じて、税理士に相続税の計算を依頼し、現状の財産状況や相続税額を元に、納税資金の準備や、節税対策のアドバイスをすることができます。 ※税金の計算は税理士業務でありFPは行えません。
- 遺留分(いりゅうぶん)への配慮: 遺言書で特定の相続人に全ての財産を相続させようとすると、他の相続人の「遺留分(法律で保障された最低限の相続分)」を侵害してしまう可能性があります。FPは、遺留分を考慮した遺言内容を検討するお手伝いをします。
- 専門家との連携: 遺言書は法的な書類です。FPは、税理士や司法書士といった専門家と連携し、より確実な形で遺言書を作成できるようサポートします。
まとめ
自筆証書遺言は、手軽に作成できる一方で、法律上のルールを守らなければ無効になってしまうリスクがあります。あなたの想いを確実に伝えるために、まずはご自身の財産を整理し、誰に何を渡したいのかを具体的に考えてみましょう。
そして、「これで大丈夫かな?」と不安になった際は、ぜひ私たちFPにご相談ください。あなたの財産と想いを守るためのサポートをさせていただきます。

