親が認知症と診断された時、多くのご家族は「どうしよう…」と途方に暮れてしまうかもしれません。しかし、これは決して他人事ではありません。人生100年時代と言われる今、誰の身にも起こりうる現実です。
大切なのは、不安な気持ちを抱え込まず、家族でしっかりと話し合い、具体的な準備を進めること。そうすることで、親の尊厳を守りながら、家族の負担を減らし、お金に関するトラブルを未然に防ぐことができるんです。
今回は、親が認知症になった時に備えて、介護とお金を守るための家族会議の進め方について詳しく解説します。
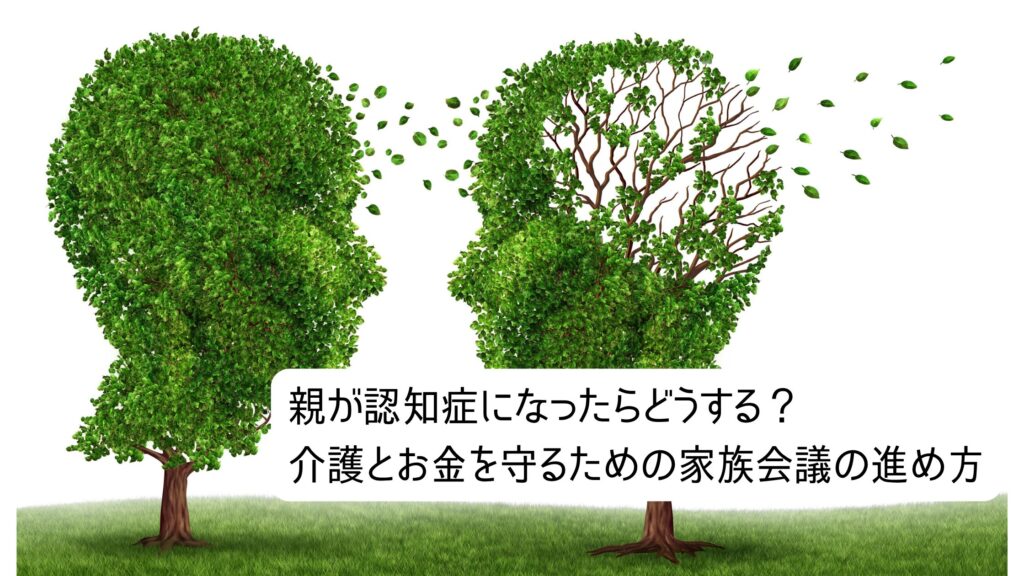
なぜ「家族会議」がそこまで重要なのか?
認知症の症状や進行の仕方は人それぞれ。だからこそ、家族間でオープンに話し合い、意思を統一しておくことが何よりも大切になります。
- 介護の方針を決めるため:
- 誰がどのくらい介護を担うのか?
- 自宅で介護するのか、施設への入居を考えるのか?
- 専門家(ケアマネジャーなど)のサポートはどこまで必要か?
具体的な介護の形を決めることで、いざという時に慌てずに済みます。
- 経済的な負担を公平にするため:
- 介護には、想像以上にお金がかかることがあります。
- 誰が費用を負担するのか、親の資産をどう活用するのか、明確にしておくことで、後々の金銭トラブルを防ぐことができます。
- 法的・財産的な準備を進めるため:
- 認知症が進むと、ご本人の判断能力が低下し、大切な契約(不動産の売買、預貯金の引き出しなど)ができなくなる可能性があります。
- 成年後見制度の利用や、家族信託など、法的な対策を事前に検討しておく必要があります。
- 家族全員の精神的負担を和らげるため:
- 家族みんなで情報を共有し、不安や意見を出し合うことで、一人で抱え込まずに済みます。
- 協力体制を築くことは、介護を続ける上での大きな支えになります。
スムーズな家族会議を進めるための4つのステップ
ステップ1:適切なタイミングと参加者の選定
- タイミング:
「もしかして?」と感じた初期段階、あるいは認知症の診断が下りた直後など、できるだけ早い時期に開催するのがベストです。ご本人の意思を尊重するためにも、判断能力があるうちに話し合いましょう。 - 参加者:
親御さん(参加可能であれば)、配偶者、兄弟姉妹など、介護や財産に関わる可能性のある主要な家族全員が参加することが理想です。遠方に住んでいても、オンライン会議などを活用して参加してもらいましょう。
ステップ2:会議前の「しっかり準備」が成功の鍵!
- 情報収集を徹底する:
認知症の種類や症状、進行度合い、利用できる介護サービス(訪問介護、デイサービスなど)、費用、そして介護保険制度や成年後見制度といった公的制度について、基本的な情報を調べておきましょう。地域の地域包括支援センターや専門機関に相談すると、具体的な情報を得られます。 - 議題を明確にする:
漠然と話し合うのではなく、「何について話し合うのか」を事前に整理しておきましょう。
例:
- 親の現状と今後予想されること
- 在宅介護か施設介護か?それぞれのメリット・デメリット
- 介護にかかる費用の見積もりと分担方法
- 親の預貯金や不動産など、財産管理について
- 延命治療など、医療に関する親の意思
- 成年後見制度など、法的手続きの必要性
- 緊急時の連絡体制
- 資料を準備する:
介護サービスのパンフレット、費用の概算表、親の資産状況がわかる資料など、具体的な数字や情報を示す資料があると、より建設的な話し合いができます。
ステップ3:いよいよ「家族会議」!穏やかに、正直に話し合おう
- 穏やかな雰囲気作り:
感情的にならず、冷静に話し合える雰囲気を作ることが大切です。全員が意見を出しやすいよう、発言を遮らず、最後まで聞く姿勢を心がけましょう。 - 本人の意思を最大限に尊重する:
親御さんが参加できる場合は、ご本人の希望や意思を何よりも大切にしましょう。「どうしたいか」を尋ね、尊厳を守ることを第一に考えます。 - オープンなコミュニケーション:
介護の負担、費用、それぞれのライフスタイルや仕事との両立など、隠さずに正直な気持ちを伝え合いましょう。 - 役割分担を具体的に決める:
「誰が、いつ、何を、どれくらい担当するのか」を具体的に決め、責任の所在を明確にすることで、「言った言わない」といったトラブルを防げます。 - 専門家の意見も取り入れる:
家族だけでは解決が難しい問題や、専門的な知識が必要な場合は、ケアマネジャー、弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナーなど、専門家を交えて話し合うことも検討しましょう。
ステップ4:介護とお金、具体的な検討事項
介護について
- 在宅介護の現実と限界:
自宅での介護がどこまで可能なのか、家族の介護負担はどのくらいになりそうか。訪問介護やデイサービス、ショートステイなど、外部サービスを積極的に利用することを検討しましょう。 - 施設介護の選択肢:
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホームなど、施設のタイプや費用、入居条件などを調べておきましょう。 - 医療体制の確認:
かかりつけ医を決め、緊急時の対応や、延命治療などの医療に関する親の意思を把握しておくことが重要です。 - ケアマネジャーとの連携:
介護保険サービスを利用する上で、ケアマネジャーは欠かせない存在です。ケアプランの作成や介護サービスの手配など、密に連携を取りましょう。
お金について
- 親の資産状況を把握する:
預貯金、不動産、有価証券、保険など、親御さんの資産全体を正確に把握します。銀行口座の場所や、可能であれば暗証番号なども確認できると、いざという時にスムーズです。 - 介護費用の捻出方法:
- 公的介護保険の活用: 要介護認定の申請を行い、自己負担割合(原則1~3割)を確認します。
- 親の資産からの捻出: 預貯金の引き出しや、必要であれば不動産の活用(売却、賃貸など)も視野に入れます。
- 家族からの援助: 兄弟姉妹間で公平な費用分担について話し合いましょう。
- 高額介護サービス費制度・高額医療費制度: 月々の自己負担額が上限を超えた場合、申請すれば払い戻しを受けられる制度です。忘れずに活用しましょう。
- 財産管理の具体的な対策:
- 家族信託(民事信託):
あらかじめ親御さんの財産を信頼できる家族(受託者)に託し、目的に沿って管理・運用してもらう制度です。例えば、「親の介護費用に充て、残った財産は子の世代に引き継ぐ」といった柔軟な財産管理が可能になります。
成年後見制度に比べて自由度が高い反面、専門知識が必要であり、信託契約書の作成には弁護士や司法書士といった専門家のサポートが不可欠です。 - 成年後見制度:
ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に申し立てて後見人(親族や弁護士、司法書士など)を選任し、ご本人の財産管理や身上監護(介護契約や医療契約など)を法的に行う制度です。
- 法定後見制度: 既に判断能力が低下している場合に利用します。
- 任意後見制度: ご本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、誰にどのようなことを任せるかを契約で決めておく制度です。
後見人は、ご本人の財産を守ることが最大の責務であり、家庭裁判所の監督を受けます。
まとめ:早く動くこと、そして助けを求めること
「まだ早いかな?」と思うかもしれませんが、早く動き出すことが、親御さんのため、そしてご自身の負担を減らすための一番の対策になります。
親が認知症になった時には既に遅く、最善の予防策を講じる事が出来ません。健全なうちに家族会議を行う事が重要です。
一人で抱え込まず、家族で話し合い、必要であれば地域包括支援センターや専門家など、外部の力を積極的に活用してください。そうすることで、親の尊厳を守りながら、家族全員が安心して穏やかな日々を送るための土台を築くことができるでしょう。
この記事が、皆さんの家族会議の一助となれば幸いです。

