「投資信託ってたくさん種類があるけど、どれを選べばいいかわからない」「投資で損したくない」
投資を始めようと考えている初心者の方にとって、投資信託選びは悩みの種ですよね。実際、数千本もある投資信託の中から自分に合ったものを見つけるのは至難の業です。
しかし、ご安心ください! 投資信託で失敗しないためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。この記事では、投資信託選びで損しないための3つのポイントを初心者の方にもわかりやすく解説します。
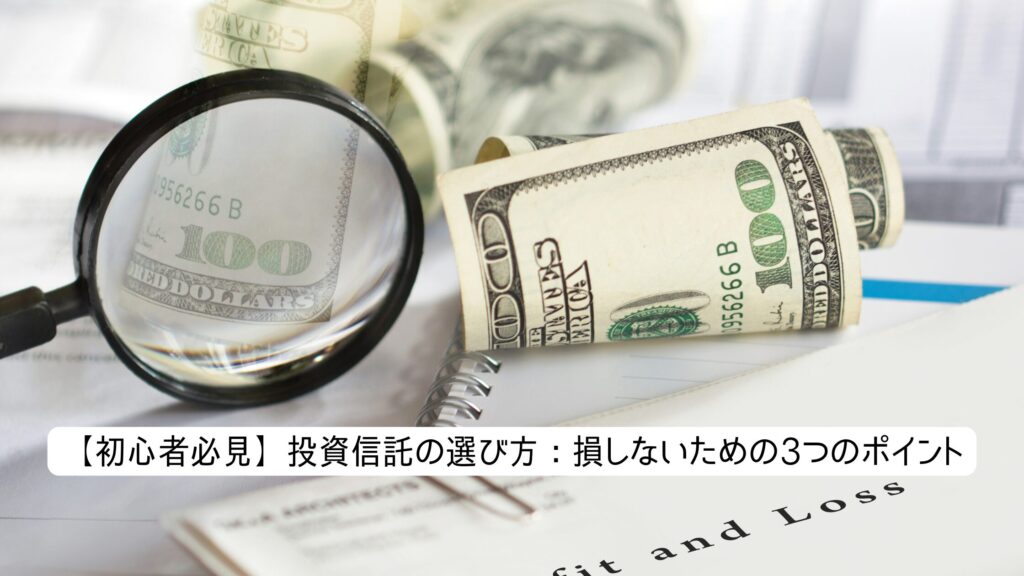
ポイント1:自分に合った「リスク許容度」を知る
投資における「リスク」とは、リターンの振れ幅のこと。ハイリスク・ハイリターンの商品もあれば、ローリスク・ローリターンの商品もあります。
まず、あなたがどれくらいの「リスク」を受け入れられるかを知ることが大切です。
- リスク許容度が高い人: 多少の元本割れは許容できるので、高いリターンを目指して積極的に運用したい。
- リスク許容度が低い人: 元本割れは極力避けたいので、リターンは小さくても安定した運用をしたい。
自分のリスク許容度を知るためには、以下の点を考えてみましょう。
- 投資の目的: 何のために投資をするのか?(例:老後資金、住宅購入資金など)
- 投資期間: どれくらいの期間、投資する予定か?(長期投資ほどリスクを抑えやすい傾向があります)
- 損失が出た場合の心理的影響: もし資産が減ってしまったら、精神的に耐えられるか?
多くの金融機関でリスク診断テストが用意されているので、活用してみるのもおすすめです。自分のリスク許容度を把握することで、無理のない投資信託選びができるようになります。
ポイント2:「コスト」を徹底的にチェックする
投資信託には、購入時や保有期間中に様々な**コスト(手数料)**がかかります。これらのコストは、運用成績に大きな影響を与えるため、必ずチェックするようにしましょう。
主なコストは以下の3つです。
- 購入時手数料(販売手数料): 投資信託を購入する際に証券会社や銀行に支払う手数料。最近は**ノーロード(購入時手数料無料)**の投資信託も増えています。
- 信託報酬: 投資信託を保有している期間中、毎日差し引かれる費用。運用管理費用とも呼ばれ、投資信託の純資産総額に対して年率でかかります。
- 信託財産留保額: 投資信託を解約する際に支払う費用。換金手数料とも呼ばれますが、設定されていない投資信託も多いです。
特に、毎日かかる信託報酬は長期保有するほど影響が大きくなります。例えば、同じような運用をしている投資信託であれば、信託報酬が低いものを選ぶのが鉄則です。わずかな差に見えても、年単位で見ると大きな差になります。
ポイント3:「分散投資」ができているか確認する
「卵を一つのカゴに盛るな」という投資の格言があるように、投資では分散投資が非常に重要です。特定の資産や地域に集中して投資すると、その対象に何かあった場合に大きな損失を被る可能性があります。
投資信託を選ぶ際も、その投資信託がどのような資産に、どのような地域に投資しているのかを確認しましょう。
- 資産の分散: 株式、債券、不動産(REIT)など、複数の資産クラスに投資しているか。
- 地域の分散: 日本国内だけでなく、先進国、新興国など、複数の地域に投資しているか。
- 時間の分散: 定期的に一定額を積み立てる「積立投資」を活用することで、高値掴みのリスクを抑え、価格変動のリスクを平準化できます。
例えば、「全世界株式」などに投資する投資信託であれば、これ一つで幅広い地域・資産に分散投資が可能です。すでに他の投資をしている場合は、ポートフォリオ全体で分散が図れているかを確認しましょう。
まとめ
投資信託選びで失敗しないための3つのポイントをまとめました。
- 自分に合った「リスク許容度」を知る
- 「コスト」を徹底的にチェックする
- 「分散投資」ができているか確認する
これらのポイントを押さえることで、初心者の方でも安心して投資信託を選び、長期的な資産形成を目指すことができます。
投資は自己責任ですが、正しい知識を身につけることで、そのリスクを軽減し、成功への道を切り開くことができます。ぜひ、この記事を参考に、あなたの投資の第一歩を踏み出してみてください。
「自分一人で投資信託を選ぶのが不安…」と感じたら、ぜひプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することをおすすめします。
FPは、あなたのライフプランや資産状況に合わせて、最適な投資戦略や具体的な投資信託選びをサポートしてくれます。納得のいく投資を行うために、FPの専門知識をぜひ活用してください。

