家計を支える上で、将来の年金は誰もが気になるテーマです。特に、専業主婦(主夫)として働いている方、あるいは、パート・アルバイトなどで働きながらも扶養に入っている方にとって、「自分の年金はどうなるのだろう?」という疑問は大きいのではないでしょうか。
今回は、主婦(主夫)の年金制度の核心である「第3号被保険者制度」について、わかりやすく解説していきます。
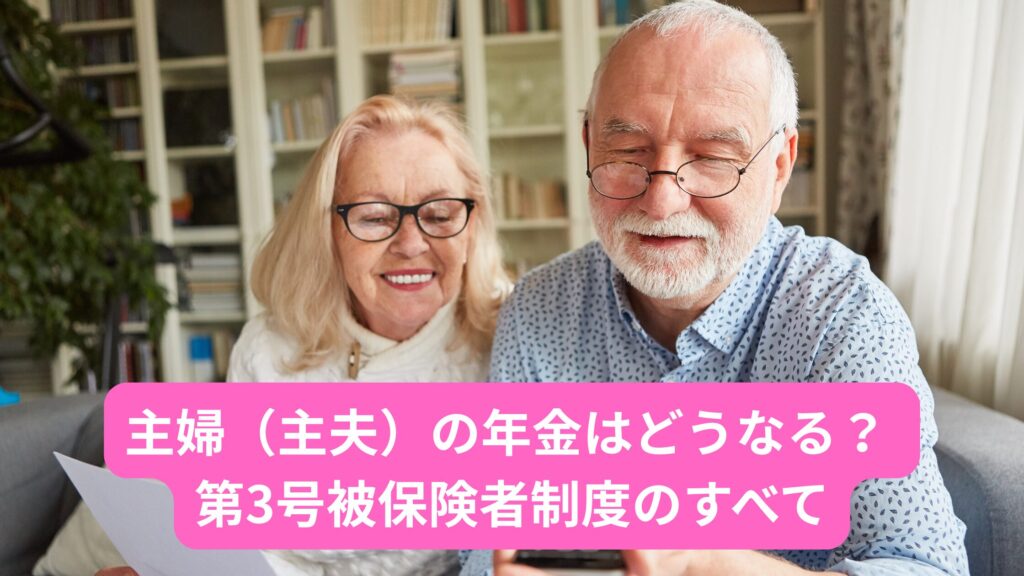
1. 日本の公的年金制度の仕組み
日本の公的年金制度は、国民全員が加入する「国民年金(1階部分)」と、会社員や公務員などが加入する「厚生年金(2階部分)」の2階建て構造になっています。
この制度において、私たち国民は主に以下の3つのグループ(被保険者)に分類されます。
| グループ | 対象者 | 支払義務 |
| 第1号被保険者 | 自営業者、自由業、学生、無職の方など | 自分で国民年金保険料を納める |
| 第2号被保険者 | 会社員、公務員など(厚生年金に加入) | 給与から厚生年金保険料が天引きされる |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 保険料の負担がない |
2. 第3号被保険者ってどんな人?
今回テーマとなる「第3号被保険者」とは、以下の条件をすべて満たす方です。
- 第2号被保険者(会社員・公務員など)の配偶者であること
- 主に日本国内に居住していること
- 年収が130万円未満であること
- 60歳以上や障害者の場合は180万円未満
- 配偶者の健康保険の扶養に入っていること
この制度の最大の特徴は、ご自身で保険料を納める必要がないにもかかわらず、将来、第1号被保険者や第2号被保険者と同じように「老齢基礎年金」を受け取ることができる点です。(なお年収制限の、いわゆる「130万円の壁」などは、今後の改正での変更が議論されています)
3. なぜ保険料を払わなくてもいいの?
「保険料を払わずに年金がもらえるなんて、どこから費用が出ているの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。
第3号被保険者の年金保険料は、個別に納めているわけではありません。第2号被保険者(夫または妻)が加入している厚生年金制度全体で負担する仕組みになっています。
<ここがポイント!>
これは、配偶者を扶養し、間接的に社会全体を支えている主婦(主夫)の貢献を評価し、社会全体で支え合うという考え方に基づいています。
4. 第3号被保険者制度を利用する上での注意点
非常にメリットの大きい第3号被保険者制度ですが、いくつか注意しておきたい点があります。
⚠️ (1) 扶養から外れる「年収の壁」に注意
第3号被保険者でいられるのは、年収が130万円未満までです。
近年、パートやアルバイトで働く主婦(主夫)の方々にとって、この「年収の壁」がより複雑になっています。特に、以下のケースでは、年収が130万円未満でも扶養から外れ、ご自身で社会保険に加入し、第3号被保険者ではなくなる(第2号被保険者になる)可能性があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円(年収約106万円)以上
- 雇用期間が2ヶ月超の見込み 等
この壁を超えてしまうと、ご自身で社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)を支払うことになりますが、その分、将来受け取れる年金(老齢厚生年金)が増えるというメリットもあります。
⚠️ (2) 離婚した場合はどうなる?
万が一、離婚した場合、第3号被保険者でいられるのは原則として離婚が成立した日までです。
離婚後は以下のいずれかの手続きが必要です。
- 第1号被保険者へ切り替え(ご自身で国民年金保険料を納める)
- 再就職して第2号被保険者へ切り替え(厚生年金に加入)
また、離婚時の年金分割制度を利用すれば、婚姻期間中の配偶者の厚生年金記録を分割し、ご自身の年金とすることができます。
⚠️ (3) 海外移住の際は要注意!
第3号被保険者の条件には、「主に日本国内に居住していること」があります。配偶者と共に海外に転居し、住民票を海外に移した場合、第3号被保険者の資格を喪失します。
海外在住中に年金を積み立てたい場合は、ご自身で任意加入被保険者として国民年金に加入し、保険料を納める必要があります。
5. まとめ
第3号被保険者制度は、専業主婦(主夫)の方々にとって、保険料の負担なしに老齢基礎年金の受給資格期間を満たせるという非常に大きなメリットがある制度です。
ただし、働き方やライフスタイルが変わると、年金の種別(1号、2号、3号)も自動的に変わるわけではなく、ご自身で手続きが必要になる場合があります。
働き始める際や、離婚、海外転居などの大きなライフイベントの際には、必ずご自身の年金種別を確認し、役場や年金事務所で必要な手続きを行うようにしましょう。
株式会社アビリティは、主婦(主夫)の皆さまのライフプランニングをサポートしています。年金についてさらに詳しく知りたい方、ご自身の将来の年金受給額を試算してみたい方は、ぜひ一度ご相談ください!

