今年も年末が近づき、そろそろ気になるのが年末調整ではないでしょうか。会社員の方にとって、年末調整は税金が戻ってくる(還付される)チャンスでもあります。その際、特に重要になってくるのが「保険料控除」です。
今回は、この「保険料控除」のうち、生命保険料控除と地震保険料控除の仕組み、手続きに欠かせない「控除証明書」、さらに具体的な控除額の計算方法と申告時の注意点について、わかりやすく解説します!
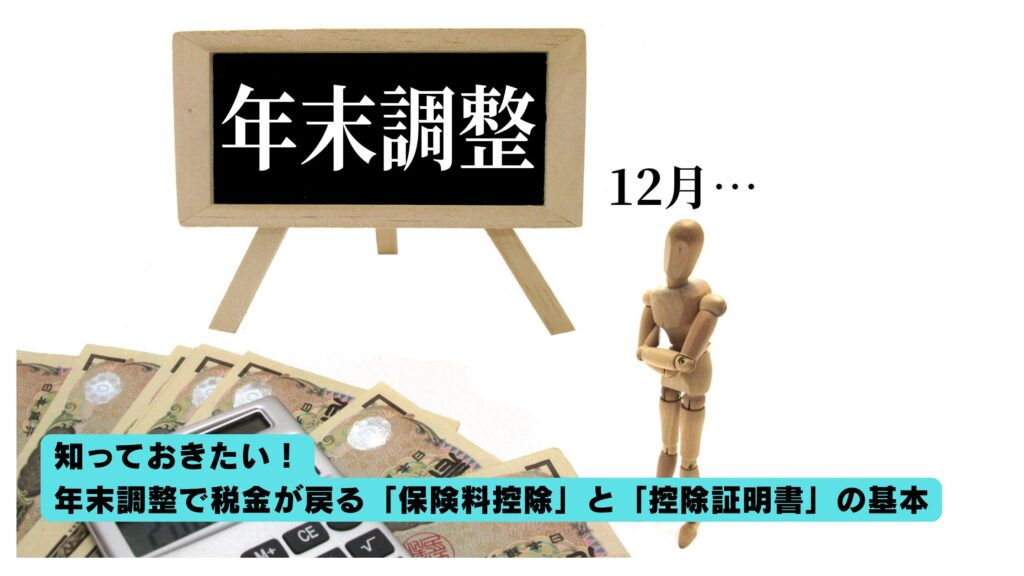
💡 そもそも「保険料控除」って何?
「保険料控除」とは、私たちが1年間に支払った特定の保険料の金額に応じて、所得から一定の金額を差し引く(控除する)ことができる制度です。
所得から控除される金額が増えるということは、課税対象となる所得が少なくなるということです。その結果、所得税や住民税の負担が軽減され、税金が還付されることにつながります。
1. 生命保険料控除の基本・計算方法(3つの区分)
生命保険料控除は、主に以下の3種類の保険が対象となり、それぞれで控除額が計算されます。
- 一般の生命保険料控除(死亡保険、養老保険など)
- 介護医療保険料控除(医療保険、がん保険、介護保険など)
- 個人年金保険料控除(所定の要件を満たした個人年金保険)
🔢 控除額の具体的な計算方法(新制度の場合)
新制度(平成24年1月1日以降契約)に基づき、控除額の計算方法を見てみましょう。
| 年間支払保険料の合計額 | 控除額(所得税) |
| 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2 + 10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料×1/4 + 20,000円 |
| 80,000円超 | 一律 40,000円 |
この計算を3区分それぞれで行い、3区分合計で所得税は最大12万円の控除となります。
また、住民税の控除額の計算方法は下記の通りです。
| 年間支払保険料の合計額 | 控除額(住民税) |
| 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料×1/2 + 6,000円 |
| 32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料×1/4 + 14,000円 |
| 56,000円超 | 一律 28,000円 |
🔢 控除額の具体的な計算方法(旧制度の場合)
同じく、旧制度(平成23年12月31日以前契約)に基づき、控除額の計算方法を見てみましょう。
| 年間正味払込保険料など | 所得税の控除額(上限:各50,000円) |
| 25,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 25,000円超 ~ 50,000円以下 | 払込保険料等×1/2+ 12,500円 |
| 50,000円超 ~ 100,000円以下 | 支払保険料×1/4 + 25,000円 |
| 100,000円超 | 一律 50,000円 |
| 年間支払保険料の合計額 | 控除額(住民税) |
| 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2 + 7,500円 |
| 40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料×1/4 + 17,500円 |
| 70,000円超 | 一律 35,000円 |
2. 地震保険料控除の基本・計算方法
火災保険とセットで加入することが多い地震保険も、控除の対象です。以前は長期損害保険も対象でしたが、現在は地震保険がメインとなっています。
📌 地震保険料控除の対象
- 地震保険
- 特定の旧長期損害保険(平成18年12月31日までに契約したもので、満期返戻金があり、保険期間が10年以上のものなど、一定の要件を満たすもの)
🔢 控除額の具体的な計算方法
地震保険料控除の計算は、生命保険料控除とは異なり、以下のシンプルな基準で行われます。
| 年間支払保険料の合計額(地震保険) | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
| 50,000円以下 | 支払保険料の全額 | 支払保険料×1/2 |
| 50,000円超 | 一律 50,000円 | 一律 25,000円 |
💡 旧長期損害保険料の控除について
旧長期損害保険料のみの支払がある場合や、地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、上記の限度額内で、有利な方を選択して申告します。最終的な控除限度額は、所得税で5万円、住民税で2万5千円です。
📄 必須アイテム!「控除証明書」と申告時の注意点
控除を受けるためには、保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」が必須です。
📅 いつ届くの?
- 多くの保険会社では、9月~11月頃に契約者宛に郵送されます。
- この証明書に記載されている「申告額」や「区分(生命保険/地震保険)」を、年末調整の申告書に正確に転記し、証明書を添付して提出します。
⚠️ 見落としがちな申告時の注意点
- 契約者(保険料負担者)を確認する
- 控除の対象となるのは、実際に保険料を支払った人(保険料負担者)です。家族の保険でも、自分の口座から引き落としていれば控除を受けられます。
- 長期一括払いの取り扱い(地震保険)
- 地震保険を数年分まとめて一括で支払った場合でも、その金額を保険期間で割って、1年当たりの金額に換算し、毎年控除を受けることができます。証明書には1年当たりの金額が記載されていることが一般的です。
- 火災保険料は対象外
- 火災保険と地震保険をセットで契約している場合、火災保険部分の保険料は控除の対象外です。控除証明書に記載されている「地震保険料」の額のみを申告しましょう。
- 証明書の再発行は早めに
- 紛失した場合は、すぐにご加入の保険会社に連絡して再発行の手続きを依頼してください。
✅ まとめ:賢く節税するために
生命保険料控除と地震保険料控除は、年末調整における大切な節税手段です。
- 「控除証明書」を必ず準備する。
- 「保険料負担者」として正確に申告する。
- 生命保険は3区分、地震保険は旧長期の有無と上限額を確認して計算する。
これらのポイントを押さえて、年末調整に臨み、申請漏れや間違いが無いようにしましょう!

