相続対策は、ご家族の将来のためにも、できるだけ早めに始めることが重要です。
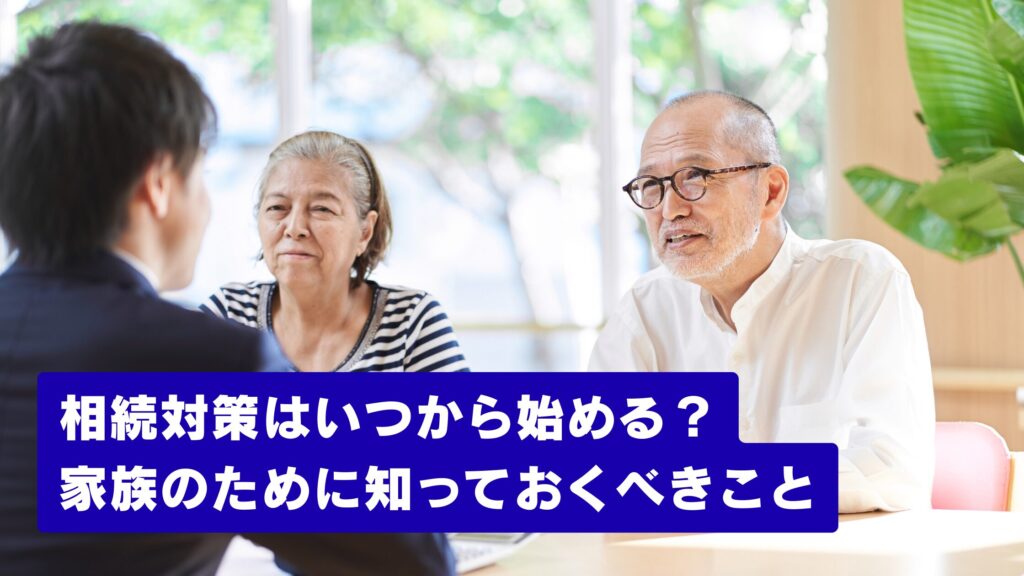
相続対策を始めるべきタイミング
結論から言うと、相続対策に「早すぎる」ということはありません。思い立ったときが吉日です。特に、以下のような時期は検討を始める良い機会です。
- 親が元気なうちに: 認知症などにより本人の意思表示が困難になると、本人が手続きを行えなくなり、口座が凍結されるリスクや、有効な遺言書の作成ができなくなってしまいます。
- 40~50代から: 親世代がまだ元気なうちに、ご自身の家族構成や親の資産状況、相続人の数などを把握しておくことが大切です。
- 60代から: 被相続人として、ご自身の資産状況に応じてどのように財産を遺すかを検討し、遺言書の作成を始める良い時期です。
- 生前贈与を検討している場合: 生前贈与には、相続開始前一定期間内の贈与が相続財産に加算される「生前贈与加算」という制度があります。この加算期間は2024年の税制改正で徐々に延長されています。そのため、早期に計画的に贈与を進めることで、節税効果を最大化できます。
家族のために知っておくべきこと
相続対策は、節税だけでなく、ご家族がトラブルなく円満に手続きを進められるように準備しておくことが何よりも大切です。
1. 財産を「見える化」する
まずは、ご自身の財産をすべて把握し、リストアップしましょう。預貯金、不動産、株式、投資信託、生命保険、デジタル資産(ネット銀行、仮想通貨など)、そして借金などの負債も漏れなく含めることが重要です。
- 財産目録の作成: どこに、どのような財産が、どのくらいの価値があるのかを明確にすることで、ご家族がスムーズに手続きを進めることができます。
- 負債の確認: ローンや連帯保証人になっている場合など、負債の状況も必ずご家族に伝えておきましょう。
2. 遺言書を作成する
遺言書は、ご自身の財産を「誰に、何を、どのくらい」遺すかを明確に示せる最も有効な手段です。特に以下のような場合は、遺言書の作成を強くおすすめします。
- 相続人以外の方(お孫さん、内縁の配偶者、お世話になった方など)に財産を遺したい場合
- 相続人間でのトラブルが予想される場合
- 特定の相続人に多く財産を遺したい場合
- 家族の中に認知症の方や未成年者がいる場合
遺言書は、ご家族との話し合いをふまえた上で、法的要件を満たした形式で作成することが重要です。公正証書遺言にすることで、内容の有効性や保管の面で安心できます。
3. 家族で話し合う
相続は、ご家族全員で考えるべきことです。しかし、切り出しにくいと感じる方も多いでしょう。以下を参考に、早いうちから話し合いの機会を設けましょう。
- エンディングノートの活用: 財産情報だけでなく、介護や医療の希望、葬儀やお墓の希望などを記しておくことで、話し合いのきっかけになります。
- 親の意思を明確にする: 親が主導して「こうしたい」という意思を伝えることで、子どもたちが自分の意見を言いやすくなります。
- 専門家の力を借りる: 税金や法律の知識が必要な場合は、弁護士や税理士などの専門家を交えて話し合うことで、スムーズかつ適切な対策を立てることができます。
4. 認知症対策も視野に入れる
認知症になると、ご自身の財産管理や各種手続きができなくなります。ご家族に負担をかけないためにも、元気なうちから対策を検討しましょう。
- 家族信託: 信頼できる家族に財産管理を任せる仕組みです。本人の意思能力がなくなっても、あらかじめ決めた通りに財産を管理・運用できます。
- 任意後見制度: 将来、判断能力が低下した場合に、誰に何を任せるかを事前に決めておく制度です。
相続対策は、ご自身の意思を反映し、残されたご家族が困らないようにするための「思いやり」です。早めに準備を始めることで、ご家族の安心につながります。
弊社アビリティでは、士業の方のご紹介も承っております。
我々もFPとしてお力になれることがありますので、お気軽にご相談ください!

